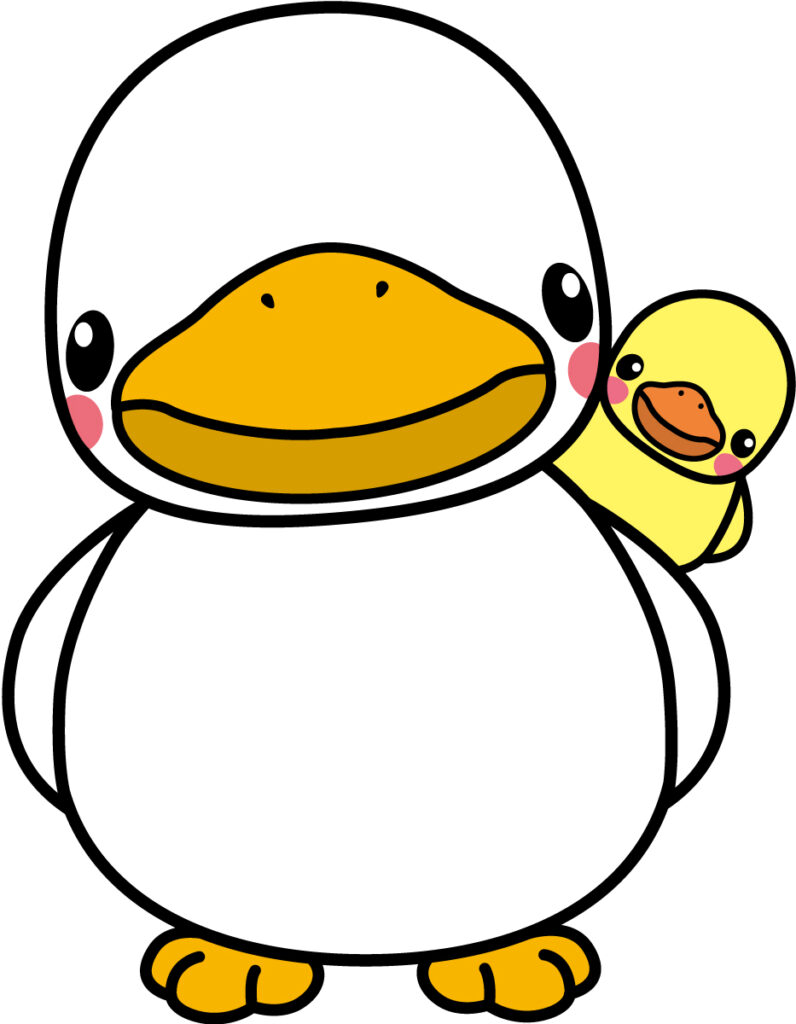アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」が話題です。しかし、これだけ注目が集まる背景には、高齢化の進行に伴う国内認知症患者数の急増があります。厚生労働省発表「高齢社会白書(平成29年)」では、認知症患者数は2025年に700万人に達し、65歳以上の20%を占めるという予測も。発症のリスクは誰もが等しく抱える以上、認知症対策は賃貸経営者にとっても他人事ではありません。
判断能力喪失によって契約が不可能に
認知症発症による最大の障害は、さまざまな「契約行為」ができなくなることです。日本の民法は契約締結において「法律行為をするうえで自己の行為の結果を判断する能力=意思能力」を必須としますが、重度の認知症患者は意思能力が“ない”と見なされ、その状態での契約は“無効”とされてしまいます。
また、認知症によって判断能力が低下し、入出金の管理もできない状態となってしまうと、せっかく積み上げた資産も凍結されたと同義です。本人名義の預貯金は、たとえ家族であっても引き出せません。
賃借人との賃貸借契約や建物修繕の契約もできない、お金も引き出せないとなれば、賃貸経営の継続はもちろん、生活を共にする家族への影響も甚大。そこで検討したいのが、判断能力の正常なうちから対策を進められる「任意後見」や「民事信託」の活用です。
発症後の対処は「法定後見」になる
賃貸経営者が重度の認知症で意思能力がないと認定された場合、一般には家庭裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選定してもらい、後見人を介して各種契約や預金の引き出しを行なうことになります。
しかし、法定後見人には本人の生活維持に必要な最低限のサポートしか許されておらず、リスクを取って収益性を高めるような投資目的の契約は行なえません。また、後見人には弁護士や司法書士が選任されることが多く、月々の報酬も必要です。何より、この法定後見制度は「事後」の対処策であり、本人が元気なうちは活用できません。

信頼する相手に経営維持を託す「任意後見」
一方の「任意後見」は、元気なうちに任意の人物と任意後見契約を締結し、いざという時に備える対策です。公正証書での契約が必要ですが、「この財産を○○なように管理してほしい」と要望を盛り込めば、法定後見よりも希望に近い形で財産管理を任せられます。
あくまで成年後見制度の範囲内のため、家庭裁判所の選定する任意後見監督人の監督を避けられず、また法定後見人と同様、任意後見人も攻めの資産運用はできませんが、裁判所が選定する後見人ではなく、自身の信頼する相手に経営を維持してもらえる安心感は大きいもの。また、法の監視の下で契約内容に応じた効力が発揮される点も一つの安心材料でしょう。
事前に将来の資産形成まで託す「民事信託」
信託とは、自身の財産の管理・運用を信頼のおける人に託す制度のこと。信託銀行等の業者に託せば商事信託、個人に託せば民事信託となり、最近では”家族”に託す民事信託「家族信託」が注目を集めています。任意後見との大きな違いは、信託契約によって受託者にさまざまな権限を与えられること。予め契約内で許諾してあれば、任意後見では制約を受ける投資的な契約も問題なく任せられます。
また、民事信託は締結後すぐに効力を発揮するため、元気なうちは自身の監督のもとで受託者に”勉強”をさせるなど、発症後に備えた賃貸経営の“引き継ぎ期間”を設ける運用も可能。一方で、受託者は長期にわたって財産管理に拘束される・発症後は受託者の裁量で資産が管理・運用され制約がない等のデメリットもあるため、活用にあたっては受託者や家族と、信託の目的や意義について十分に話し合っておくことが重要です。

任意後見と民事信託、どちらを採用するにしても、認知症を発症してからでは対策ができません。また、財産管理を託した先には必ず「相続」の問題が発生します。認知症対策は相続対策とワンセットで考え、早めの計画・準備を心掛けましょう。